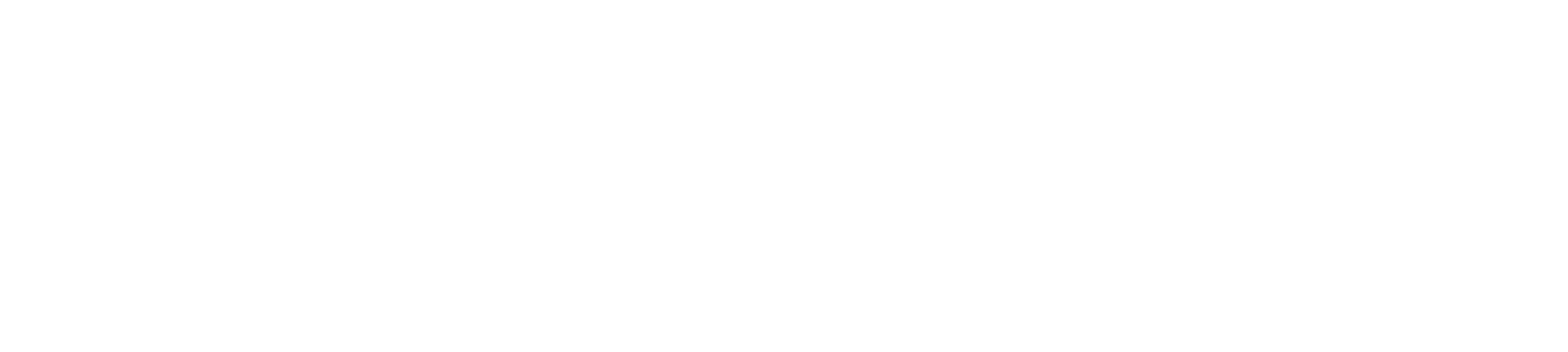歩み
2003年4月に設立したメハラ修道院は、2023年4月13日閉院いたしました。
医師でもあった一人の姉妹が、1991年から年に1~2回、1回約1ケ月の間、東ティモールで医療奉仕をしていました。
1998年 東ティモールのサレジオ会司祭から修道院設立の招待状を受けました。会員数名が現地を視察。
色々な体験を通して神からの招きとして受け止め、修道院設立を決定しました。
1999年から日本の信徒宣教者(東ティモール医療友の会(当時)現・特定非営利活動法人AFMET)の活動が始まりました。
その関わりから2003年4月東ティモールの東部にあるラウテン県メハラ村に聖母訪問会修道院を開きました。
インドネシアからの独立間もない時から村の人々と共に歩み始めました。
若者の育成、教会奉仕、村人を訪問(看護・介護・聴き手など)を使命とし、活動してまいりました。
活動時の様子
私たちの小さな働きを、賢治の詩のリズムを拝借してお届けします。
村に病人が出たと聞くと、
きれいな水と砂糖を持ってお見舞いに行き、
ハコイ(葬式)があると聞くと、かけつけ、
フェリク(婦人)たちと一緒に食べ物の準備をし、
家族が面倒を見切れない障害者の所には、
バケツと雑巾とご飯を持って訪問し、
この村から車で6時間離れている首都ディリが
どうも治安が不安定になってきているらしいと聞くと、
村人と一緒にロザリオで祈って、主に憐れみを願う。
田んぼが豊作と聞くと、自分の事のように大喜びして、
雨が続くと、
あのお年よりの小さなあばら屋は
どうなっているかなと眠れなくなり・・・
修道院の畑の野菜の収穫が多い日には、
トースナイン(農夫)さんと一緒に
手押し車に乗せて配り歩き、
寂しい人、悲しんでいる人がいると聞くと、
若い志願者と家庭を訪問して、
みんなで幸せを分かち、祈り合う。
村ごとに違う言葉が通じなくて悲しくなった日、
文化の違いに行き詰った時には、
夜空に溢れる星を眺めて慰められ・・・
体調が優れない時には
自分の限界をわきまえて、
独り静かに木陰で休み・・・
遠い日本がふと懐かしくなる時もあります。
種からパパイアが実ったり、オクラを普及させたり、
日本からのダリアの花が咲いて村の人にも楽しんでもらったり・・・
足りない共同体を支えて下さる神さまにただただ頭を垂れ、
朝5時からの祈りで毎日がスタートします。
その日の歩みは神さまにしか分からない、
完全に自由な奉献の日々です。
こんなに地味な宣教ですが、
長~~い歴史を司るのは、この宇宙をお創りになった神さまです。
その永久の救いの歴史の中に、
私たちの一滴の足跡も残っていくのでしょうか。
「マードレ!マードレ!」と子ども達も、
小さなパイナップルを届けてくれます。